【インフレで深刻化する生活格差】永濱利廣氏/中間層を「スクリューフレーション」が直撃/新興国台頭で食料・エネルギー高騰/年収別で格差?富裕層も減少/個人消費も⇩では7月の日銀で利上げ早い│日経CNBC
Summary
TLDRゲストの長浜俊博さんは、インフレが深刻化する生活格差について語ります。日本だけでなく、世界中で10年以上前から進行しており、特に2010年頃から。新興国の市場経済への参入とグローバル企業の影響で、食料やエネルギー価格が上昇。これにより、所得階層による生活必需品と贅沢品の価格格差が広がり、低所得世帯の負担が増大。地域別にも物価の差があり、北海道や東北、沖縄の上昇幅が大きい。物価上昇はコストプッシュ的で、実質賃金がマイナスで消費が落ち込んでいる。日銀の利上げについても、効果や影響が不透明で、経済全体に与える影響が懸念される。
Takeaways
- 🌐 インフレは日本だけでなく、世界中で10年以上前から問題となっている。
- 📉 スクリーンの言葉は、中間層を締めつけるインフレのことを指しており、2010年頃から始まっている。
- 🏭 市場経済への新興国の参入とグローバル企業の進出が、労働力の安い国での製品輸出と生活水準の向上をもたらした。
- 📈 食料やエネルギーの消費が増えたことで、世界的な需要が増し、価格が上昇した。
- 📊 グラフによると、生活必需品と贅沢品の価格の差が広がり、2010年代以降特に顕著だ。
- 💰所得が低い世帯では生活必需品の支出が高く、物価の上昇により生活格差が拡大している。
- 📈 2022年以降、生活必需品の価格が急激に上昇している。
- 🌍 地域別に見ると、北海道や東北などの寒冷地や沖縄のような高消費地域で物価上昇幅が大きい。
- 💡 物価の上昇は、主にエネルギー価格の影響で、地域別の消費者物価指数(CPI)にも影響を与えている。
- 📊 所得階層別の消費者物価指数(CPI)によると、年収が低い層では生活必需品の価格上昇の影響が大きい。
- 🏛️ 日本の所得格差が拡大しているが、これは中間層の削減ではなく、全体の貧困化に近い状況である。
Q & A
ゲストの専門分野は何ですか?
-ゲストの専門分野は経済学であり、特に第1生命経済研究所の主席エコノミストである長浜俊博さんです。
インフレが深刻化する生活格差とはどのような問題ですか?
-インフレが深刻化する生活格差とは、物価の上昇によって生活必需品と贅沢品の価格差が広がり、所得階層によって消費パターンに差が生じ、特に中低所得層が生活に苦しむ問題を指します。
スクリーフレーションとはどのような概念ですか?
-スクリーフレーションとは、社会の中間層が圧迫され、その結果として所得格差が拡大する社会現象を指します。
2010年頃から始まったとされるスクリーフレーションの原因は何ですか?
-2010年頃から始まったスクリーフレーションの原因は、新興国の市場経済への参入とグローバル企業の進出、それに伴う新興国の労働力の低廉化、製品の輸出、生活水準の向上、食料やエネルギーの需要増加などが挙げられます。
生活必需品と贅沢品の価格差が広がる現象はどのように影響を及ぼしていますか?
-生活必需品と贅沢品の価格差が広がることで、所得階層によって消費への影響が異なり、特に低所得層が生活必需品への費用を多く負担し、生活格差が拡大する影響を及ぼしています。
所得階層による生活必需品への費用のウェイトはどのように異なりますか?
-年収200万円未満の低所得層では生活必需品へのウェイトが6割近くにのぼり、必要なものを購入する必要性が高いのに対し、年収1500万以上の高所得層では生活必需品へのウェイトは4割ちょっと程度で、生活質への影響は小さく抑えられています。
地域別に物価の上昇幅にはどのような差はありますか?
-地域別に物価の上昇幅には差があります。北海道や東北は寒冷地であることやエネルギー消費量の高さから物価の上昇幅が大きく、一方で北陸は水力発電の割合が高く化石燃料の値上がりの影響が小さく、物価上昇幅が小さい傾向にあります。
物価上昇が生活格差に与える影響とはどのようなものですか?
-物価上昇が生活格差に与える影響は、所得階層によって生活必需品への費用のウェイトが異なり、特に中低所得層の人々が生活必需品への負担を多く感じることで、既存の所得格差をさらに拡大する可能性があるというものです。
日本銀行の金融政策決定にどのような問題が考えられますか?
-日本銀行の金融政策決定では、物価上昇がコストプッシュ的であること、円安の背景にあるインポート物価の上昇、実質賃金の低下、消費の低迷、金利上昇による経済への影響などが考慮されなければならない問題点です。
インフレ率の変動が示す経済状況はどう解釈されますか?
-インフレ率の変動は、物価上昇が需給バランスやコストプッシュ的要因によるものであることを示し、経済全体の消費活動や実質賃金の動向を反映しています。
日本の食料・エネルギー受給率の低さはインフレにどのような影響を与えますか?
-日本の食料・エネルギー受給率が低いことにより、国際市場の動向により直接的に物価が影響を受けやすくなり、インフレ率が高まることが多くなる影響を与えています。
利上げが行われた場合の影響はどのように考えられますか?
-利上げが行われた場合、円安を抑えることができる可能性があるものの、不確実性が高いと同時に、金利の上昇によって消費活動や経済全体にマイナスの影響を与える可能性があります。
現在の経済状況下で消費者物価指数(CPI)はどのように動いていますか?
-現在の経済状況下でCPIは物価上昇の中でも食料やエネルギーの価格上昇に大きく影響されており、これにより生活必需品への負担が増し、特に低所得層に影響が大きいと動き出しています。
Outlines
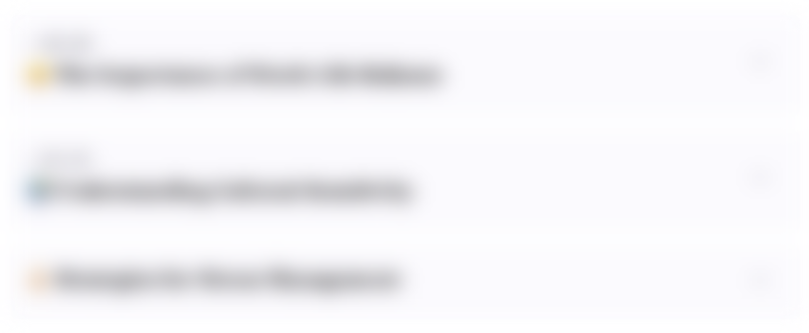
Cette section est réservée aux utilisateurs payants. Améliorez votre compte pour accéder à cette section.
Améliorer maintenantMindmap

Cette section est réservée aux utilisateurs payants. Améliorez votre compte pour accéder à cette section.
Améliorer maintenantKeywords

Cette section est réservée aux utilisateurs payants. Améliorez votre compte pour accéder à cette section.
Améliorer maintenantHighlights
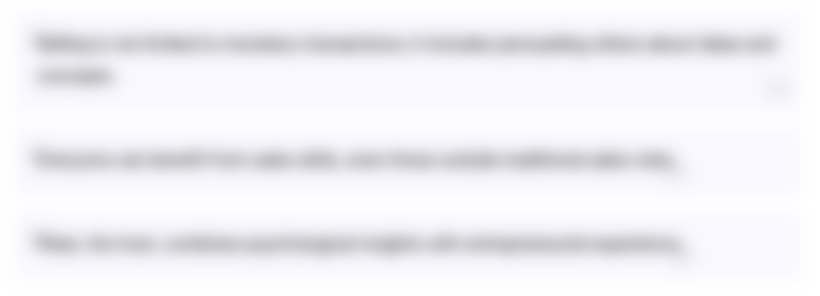
Cette section est réservée aux utilisateurs payants. Améliorez votre compte pour accéder à cette section.
Améliorer maintenantTranscripts
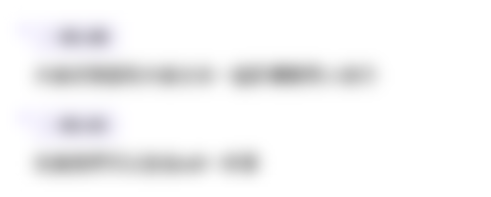
Cette section est réservée aux utilisateurs payants. Améliorez votre compte pour accéder à cette section.
Améliorer maintenantVoir Plus de Vidéos Connexes

【住所特定】家バレどう防ぐ?タクシー&配達も警戒?縦型のTikTokは情報量が?柴田阿弥&芳賀セブン|アベプラ

浜崎洋介:不可知で神秘的な人生 前編

【チョコザップ】RIZAPのDX本部長インタビュー。「chocoZAP」大ヒットの裏側をサトマイが探ります

【キーエンスに学ぶ①】付加価値とは何か?/付加価値とムダの違い/価格を下げると、利益は格段に下がる/顕在ニーズと潜在ニーズ/付加価値アップのカギは感情にある/3種類の付加価値【カクシン田尻望】
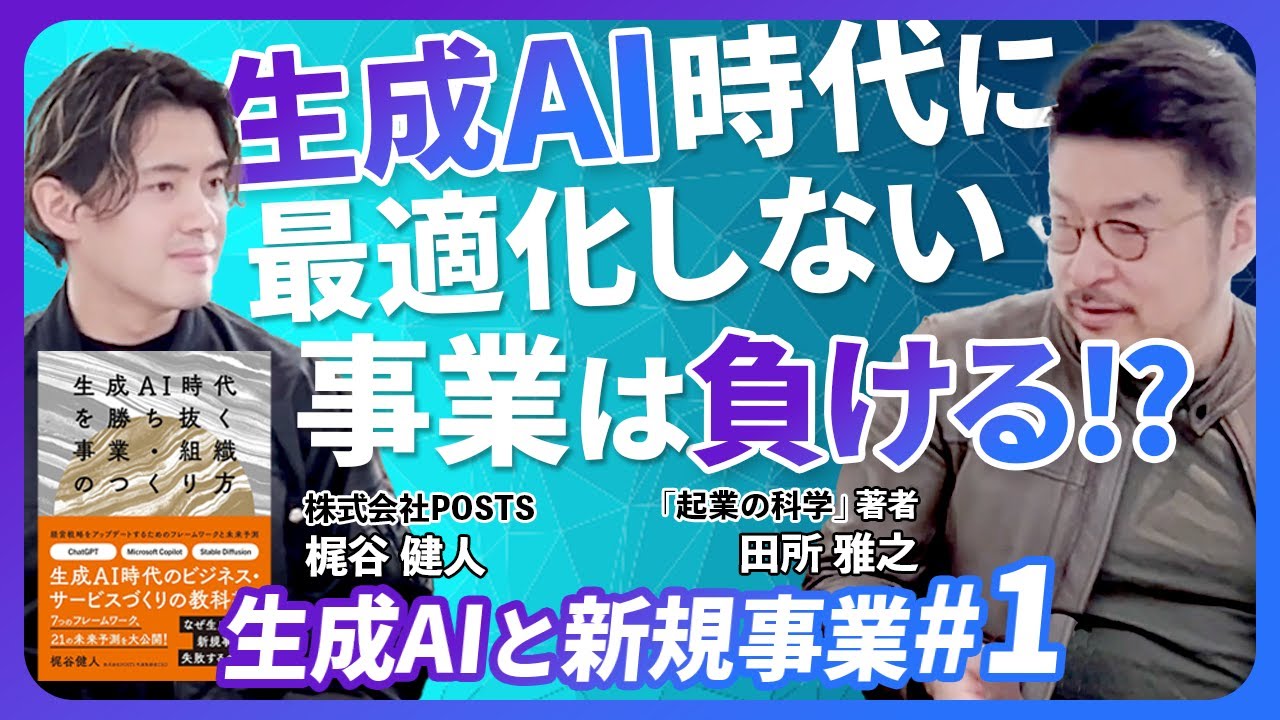
【 生成AI と 新規事業 】新シリーズ始動!「生成 AI 時代を勝ち抜く事業・組織の作り方」 梶谷健人 さんをゲストにお迎えして 生成 AI の今の実力を語ります。

【ひろゆき】※この人は本当にすごい※タモリの発言に背筋が凍りました。"あの一言"である人の人生が変わったんですよね。【ひろゆき切り抜き/いいとも/テレフォンショッキング/黒柳徹子/西野/プペル】
5.0 / 5 (0 votes)
