【保存版】2024年以降の相続時精算課税制度を徹底解説!押さえておくべき制度の概要&視聴者の方からよく聞かれる質問7選
【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所
30 Mar 202456:33
Summary
TLDRこの動画では、2024年以降の相続時生産課税制度の概要と利用上の注意点について解説しています。新たに設けられた110万円の非課税枠や相続税の節税効果、歴年増与との併用方法など、視聴者のよく寄せられる7つの質問に答えます。税理士の秋山が、生前増与の適切な戦略を提言し、多くの家庭が相続税を節約できる機会を逃さないように導線を提供します。
Takeaways
- 😀 2024年1月1日から相続時生産課税制度が大幅に改良され、より使いやすくなりました。
- 📈 相続開始前の歴年増与の足し期間が従来の3年から7年に延長され、解約増税の可能性が高まります。
- 💰 相続時生産課税制度に年間110万円の非課税枠が設けられ、申告不要の範囲が拡大しました。
- 🏦 相続時生産課税制度の対象となる財産は現金以外にも有価証券、不動産、宝石、車など多岐にわたります。
- 🔄 相続時生産課税制度を利用することで、将来の相続税の節税効果が得られるようになりました。
- 📉 過去の増与税の申告義務が緩和され、110万円以下の増与については申告不要になりました。
- 👨👧👦 相続時生産課税制度は直系卑属間の贈与に限定され、法定相続人以外の相続も対象となります。
- 🏠 自宅の不動産を増与することで相続時の相続税を回避することができる一方、将来的に小規模宅地等の特例が使えなくなることがあります。
- 📋 相続時生産課税制度を利用する際には、増与税の申告書や相続時生産課税選択届け出書、戸籍本などの書類が必要になります。
- 🚫 相続時生産課税制度を一度選択すると、同じ双方向の関係で歴年増与に戻ることはできなくなります。
- 🤔 相続時生産課税制度の利用は、財産の性質や将来の相続税の節税効果、手続きの煩雑さを考慮した上で判断する必要があります。
The video is abnormal, and we are working hard to fix it.
Please replace the link and try again.
Please replace the link and try again.
Outlines
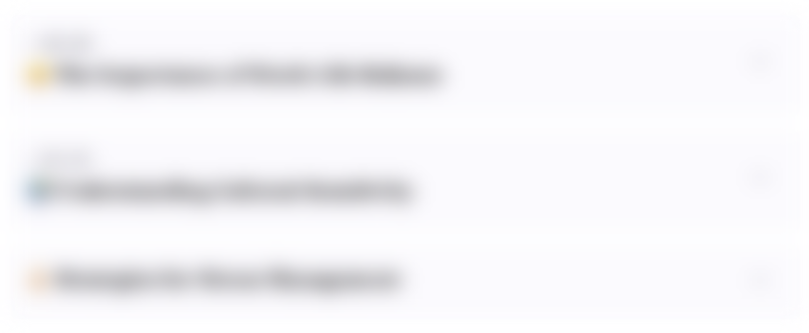
このセクションは有料ユーザー限定です。 アクセスするには、アップグレードをお願いします。
今すぐアップグレードMindmap

このセクションは有料ユーザー限定です。 アクセスするには、アップグレードをお願いします。
今すぐアップグレードKeywords

このセクションは有料ユーザー限定です。 アクセスするには、アップグレードをお願いします。
今すぐアップグレードHighlights
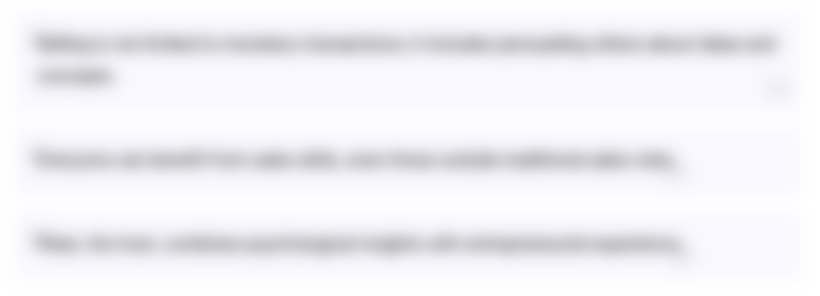
このセクションは有料ユーザー限定です。 アクセスするには、アップグレードをお願いします。
今すぐアップグレードTranscripts
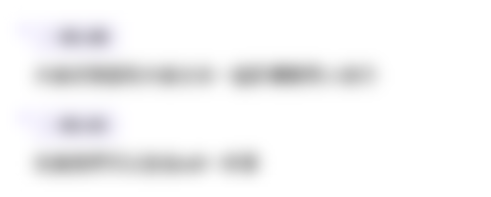
このセクションは有料ユーザー限定です。 アクセスするには、アップグレードをお願いします。
今すぐアップグレードRate This
★
★
★
★
★
5.0 / 5 (0 votes)
関連タグ
相続税税理士生前贈与非課税枠節税相続計画制度変更財産移転増与税相続トラブル





