小中学生の不登校が“過去最多”に…「もう一度学びの楽しさを」家庭・学校以外の“第3の居場所”どう作る?【news23】|TBS NEWS DIG
Summary
TLDR熊本市の小学生、山口風太さんは発達障害で長年学校を休学。自宅で過ごす日々が続き、母親は将来への不安を抱えていた。しかし、熊本学習支援センターのフリースクールで自分に合ったペースで学び、自信をつける。中心は大学生のボランティアによる個別指導。不登校の子供たちに学ぶ機会を提供し、自宅で過ごす子供向けにオンライン授業も開始。不登校の増加に伴い、保護者も困難に直面。文部科学省は教育機会確保法を転換し、様々な学びの場を確保する方針。フリースクールは有料のため、経済的支援も求められる。
Takeaways
- 🏠 山口風太さんは熊本市の小学6年生で、長年学校に通っておらず、発達障害と診断されています。
- 📚 風太さんは特別支援学級になじめず、家で漫画を読んだりゲームをしたりして過ごしていました。
- 👩 母親は風太さんが学校に行かず、将来に不安を感じています。
- 📉 2021年度の不登校小中学生は24万5000人と過去最多となり、自宅で過ごす割合が9割に上ります。
- 🏫 風太さんは熊本市内のフリースクール「熊本学習支援センター」に通い始め、自主的な学習を楽しんでいます。
- 👥 センターでは小学生から高校生までが一緒に過ごし、大学生のボランティアが個別に教えています。
- 🌳 センターでは勉強だけでなく、遊びや食事を通じて子どもたちの福祉も大切にしています。
- 👦 風太さんの母親はフリースクールでの経験が風太さんの自信をつけさせて、自宅で過ごすより良い影響を与えていると感じています。
- 💻 熊本市で不登校児童向けのオンライン授業が展開され、自宅から参加できる柔軟な形式で行われています。
- 👩🏫 再雇用された60代の教師3人が1000人の不登校児童を担当し、オンライン授業を通じて学びの楽しさとつながりを伝えています。
- 🔄 不登校の状況は9年連続で増加しており、特に小学生の割合が大きく、さまざまな支援が必要とされています。
- 🤔 不登校の子どもたちには学校以外の「第三の居場所」が必要な時代が到来しているとの見方があります。
- 📈 民間フリースクールは有料であるため、自治体が経済的支援を提供するケースもありますが、まだ普及していないと感じています。
- 🛣️ 文部科学省は不登校対策の方針転換しており、学校以外の学びの場を確保することが国の目標となっています。
Q & A
山口風太さんはなぜ学校に行きたくなくなりましたか?
-風太さんは発達障害と診断されており、特別支援学級などにもなじめずに、学校に行きたくなくなった理由を自分でも覚えていないようです。
風太さんは学校に行かず、家で何をしていますか?
-風太さんは家で漫画を読んだりゲームをしたりして過ごしており、特別な支援を受けることができませんでした。
風太さんの母親が抱えていた不安は何ですか?
-風太さんの母親は、彼が学校に行かず、掛け算など基本的な学力を身につけずに大人になることに不安を感じていました。
2021年度の不登校の小中学生の数はどのくらいですか?
-2021年度の不登校の小中学生は、およそ24万5000人と過去最多となっています。
不登校時の子供たちが主にどこで過ごしていると民間調査によると?
-民間調査によると、不登校時の9割の子供たちが主に自宅で過ごしていると報告されています。
風太さんが通っている熊本学習支援センターの特徴は何ですか?
-熊本学習支援センターは決まったスケジュールがなく、子供たちが自分のペースで学ぶことができるフリースクールです。
熊本学習支援センターではどのような形で勉強を教えていますか?
-センターでは小学生から高校生までが一緒に過ごし、大学生のボランティアが中心となって個別に勉強を教えています。
風太さんの母親がフリースクールに通い始めてから感じた変化は何ですか?
-風太さんの母親はフリースクールに通い始めてから、風太さんに自信がついてきてることが感じられています。
熊本市で配信されている不登校児童向けのオンライン授業の特徴は何ですか?
-熊本市で配信されているオンライン授業は、不登校児童が自宅など好きな場所から参加し、チャットや学習支援アプリを使ってやり取りすることができます。
不登校児童向けのオンライン授業はどのようにして受講生に配慮していますか?
-オンライン授業では、子どもたちが参加しやすいように、なぞなぞや雑談も取り入れ、堅苦しくない授業を心がけています。
不登校の子供たちが直面する課題には何がありますか?
-不登校の子供たちは学習だけでなく、家庭の経済的支援や親が働けなくなるなどの問題に直面しています。
フリースクールの運営にあたっての課題とは何ですか?
-フリースクールは基本的に有料であるため、一部の家庭には経済的な負担がかかることがあるという課題があります。
文部科学省は不登校の子供たちに対する方針をどのように転換していますか?
-文部科学省は2016年の教育機会確保法で、不登校の子供たちが学校に戻ることが全てではないと方針を転換し、様々な学びの場を確保することが国が目標としています。
Outlines
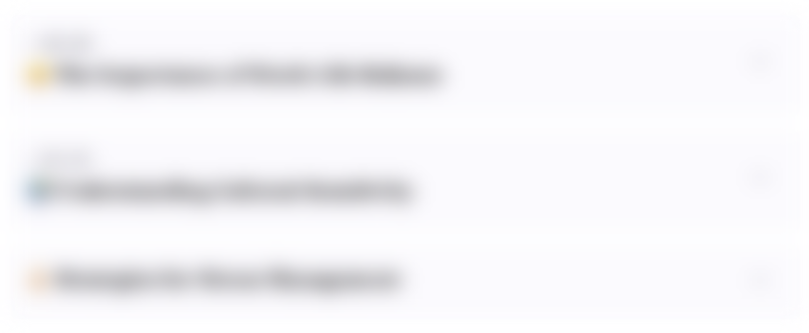
This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.
Upgrade NowMindmap

This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.
Upgrade NowKeywords

This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.
Upgrade NowHighlights
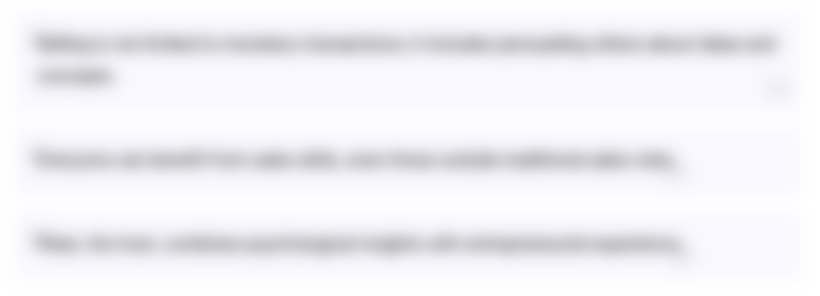
This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.
Upgrade NowTranscripts
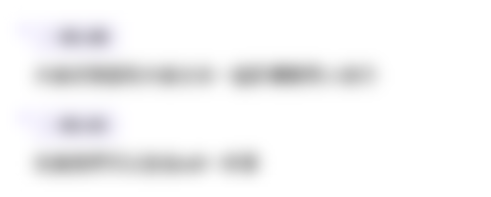
This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.
Upgrade Now5.0 / 5 (0 votes)






