【介護入門①】いつかは訪れる親の介護に今から備えておこう!
Summary
TLDRこのビデオのスクリプトは、介護が必要になった場合の手続きと注意点について説明しています。 まず介護保険制度を利用するための申請手続きを行い、要介護度の認定を受ける。その後、ケアプラン作成のサポートを地域包括支援センターから受けたり、ケアマネージャーに依頼したりできる。費用面では本人の貯蓄を100歳までのプランで割り振るなど、計画的な予算配分が大切。家族だけでなく制度やサービスを利用し、介護をチームで支えることが重要だと指摘している。
Takeaways
- 😊 介護が必要になったら、介護保険制度を利用することが大切
- 📝 要介護認定の手続きを踏む必要がある
- 🗂 地域包括支援センターが介護の相談にのってくれる
- 💰 介護にかかる費用を親の年金や貯金などから支払う
- 📈 親の生涯設計に基づいて介護の予算を立てる
- 👪 介護を一人で抱え込まずに助けを求める
- 🏢 介護休暇を取得しながら仕事も続ける
- 🔨 住宅改修費用の助成制度もある
- 🗒️ 親の日常で気になる点はメモしておく
- ✍️ 後編では在宅介護と施設利用の選択肢が詳しく解説される
Q & A
介護保険制度とはどのようなものですか?
-65歳以上の方を対象とした公的な介護サービスを受けるための制度です。介護が必要になった場合に、介護認定を受けることで、介護サービスの利用や補助金の交付を受けられます。
介護認定とは何のことですか?
-要介護状態かどうかを判断し、必要な介護の程度を区分することです。調査の結果、要介護1から5までのいずれかの認定を受けます。数字が大きいほど介護度が高いことを示します。
地域包括支援センターとはどこですか?
-地域の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、介護や福祉の相談に応じたり、サービスにつなげたりする総合支援機関です。
ケアマネージャーとは何をする人ですか?
-利用者の状況に合わせた介護サービス計画を作成し、介護サービス事業者と連携を図る専門職です。利用者の希望をくみ取り、最適な介護プランを立てます。
介護保険を受給するにはどうしたら良いですか?
-まず65歳以上であることが条件です。自治体に介護保険の申請を行い、要介護認定の審査を受ける必要があります。認定されると、保険給付の対象となります。
介護サービスにかかる費用はどのように支払うのですか?
-利用者が1割を自己負担として支払い、残りの9割が介護保険から給付されます。サービスによっては上限額が設けられています。利用者の所得によっては2割負担となる場合もあります。
認知症の人を介護する際に注意することは何ですか?
-認知症の人はプライドが高く、自分の障害を隠そうとする場合があります。実際の状況を正確に判断するためには、日頃の様子を記録しておくことが大切です。
介護にかかる費用をどのように見積もれば良いですか?
-まず現在の収入と貯蓄額を確認します。その上で、要介護者の平均余命を考慮して必要な介護費用を試算していきます。100歳まで生きることを前提に計画するのが賢明です。
介護で仕事を辞めずにすむ方法はありますか?
-法律で定められた「介護休業制度」を利用することができます。要介護状態が認定されていれば、年間で最大93日の休業取得が可能です。休業中の所得補償もあります。
親の介護は一人でするべきなのでしょうか?
-決してそうではありません。家族や親戚、地域の人々、そして国の制度など、周囲の支援を得ることが大切です。一人で背負うことだけは避けるべきです。
Outlines
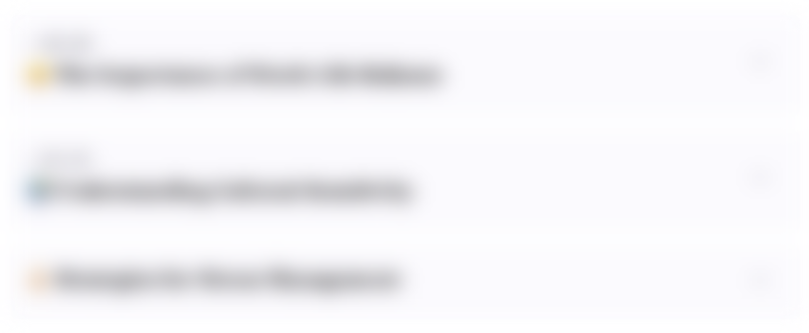
このセクションは有料ユーザー限定です。 アクセスするには、アップグレードをお願いします。
今すぐアップグレードMindmap

このセクションは有料ユーザー限定です。 アクセスするには、アップグレードをお願いします。
今すぐアップグレードKeywords

このセクションは有料ユーザー限定です。 アクセスするには、アップグレードをお願いします。
今すぐアップグレードHighlights
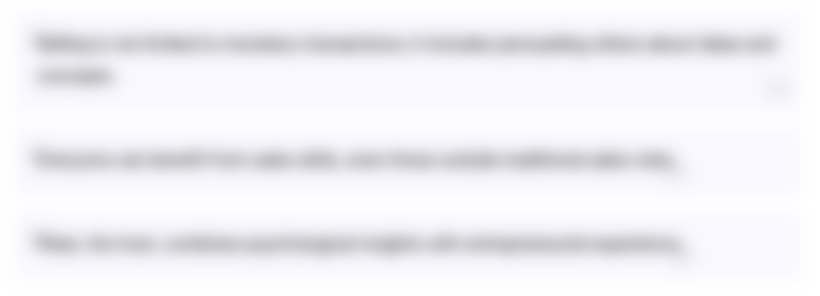
このセクションは有料ユーザー限定です。 アクセスするには、アップグレードをお願いします。
今すぐアップグレードTranscripts
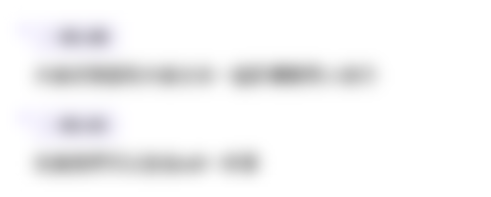
このセクションは有料ユーザー限定です。 アクセスするには、アップグレードをお願いします。
今すぐアップグレード5.0 / 5 (0 votes)






