【ゆっくり解説】海の生物が溶ける⁉「海洋酸性化」の恐ろしさとは?を解説/プランクトン・サンゴから捕食者へ波及…生態系への影響と対策
Summary
TLDRこの動画では海洋酸性化の現状とその影響について解説しています。地球温暖化に伴い、海水温が上昇し、海面水位が高まり、海洋酸性化が進んでいると警告します。海洋生物の多様性に大きな影響を与え、特に珊瑚や貝類の生態系に深刻な影響が懸念されています。また、漁業や経済活動にも大きな影響が予想されており、二酸化炭素排出の削減や低炭素社会の実現が急務となっています。さらに、SDGs達成のための取り組みや企業の脱炭素取り組みの紹介もされています。
Takeaways
- 🌊 海洋酸性化は、海水が酸性に近づく現象で、地球全体で急速に進行中であるとされている。
- 📉 pH値の低下は、産業革命以後の急激なペースで進んでいると気象庁のデータから読み取れる。
- 🌡️ 特に冷たい海域である北極や南極では、二酸化炭素の吸収率が高く、酸性化が進んでいる。
- 🐚 海洋酸性化は、サンゴや貝類、甲殻類などの生物に直接的な影響を与え、生態系に大きな影響を及ぼす。
- 🦀 酸性化により、生物の骨格や殻が形成困難になり、捕食者に対する防御力が低下する。
- 🌿 プランクトンの減少は、魚介類の成長に影響を与え、最終的には食物連鎖全体に影響を及ぼす。
- 💡 海洋酸性化は、漁業や水産業に経済的な損失をもたらし、食糧の供給に関わる重要な問題となっている。
- 🌱 マングローブなどの海岸植物は、二酸化炭素の吸収に大きな役割を果たし、脱炭素社会の実現に寄与する。
- 🔧 パリ協定に基づく温室効果ガス排出削減は、海洋酸性化を抑制するために国際社会が取り組む課題。
- 🌐 SDGsの目標14は、海洋の豊かさを守り、持続可能な海洋資源の利用を目指している。
- 📊 海洋酸性化は過去3億年来で最も急速なペースで進行しており、地球の未来に関わる重要な問題である。
Q & A
海洋酸性化とはどのような現象ですか?
-海洋酸性化とは、海水が酸性になる、または酸性に近づいていく現象です。これは主に大気中の二酸化炭素が海に吸収され、炭酸として変化し、水素イオンの濃度が増加することにより起こります。
海洋酸性化が進むと、どのような影響が生じる予測がありますか?
-海洋酸性化が進むと、海の生き物たちの5分の1が消滅するという予測があります。また、私たちが食べている海の幸も激減する可能性があります。
pHとはどのような単位で、どのようにして液体のアルカリ性や酸性を示しますか?
-pHとは、液体がアルカリ性なのか酸性なのかを示す単位で、水素イオンの濃度の度合いを表します。pHの数値が高いほどアルカリ性を示し、低いほど酸性に近づくようになります。
地球の初期の海はどのような状態でしたか?
-地球の初期の海は酸性の海で、雨に溶けた様々な物質によって形成されました。その後、地表のカルシウムや鉄、ナトリウムなどが溶かし、中和されて現在の弱アルカリ性の海となりました。
海洋酸性化の進展速度は過去に比べてどのくらい速いですか?
-海洋酸性化の進展速度は、産業革命以降250年間の10年あたりの平均値に比べて4.5倍のペースで進行しているとされています。
二酸化炭素が海に吸収されるとどのような変化が起きますか?
-二酸化炭素が海に吸収されると、一部が炭酸になり、さらに炭酸が分離し、結果的に水素イオンが増加します。この水素イオンが増加することにより海水の酸性が高まります。
海洋酸性化が珊瑚に与える影響とは何ですか?
-海洋酸性化が進むと、珊瑚が自分の骨格を作る石灰化のプロセスを阻害され、既存の珊瑚礁が溶け出す現象が起こり、珊瑚礁の破壊につながります。
海洋酸性化が進むと、どのような経済的影響が予想されますか?
-海洋酸性化が進むと、エビやカニ、ホタテ、アワビなどの水産物が少なくなり、漁獲量の減少が予想され、経済損失が大きいと懸念されています。
海洋酸性化に対抗するために、どのような国際的な取り組みが行われていますか?
-海洋酸性化に対抗するために、パリ協定という国際的な温室効果ガス排出量削減の取り組みが行われています。これは地球温暖化を防ぐために、世界各国が温室効果ガス排出量を削減することを目指した協定です。
日本政府は脱炭素社会の実現に向けてどのような目標を設定していますか?
-日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにし、脱炭素社会を実現させることを目標としています。これは、排出と吸収のバランスが取れている状態、すなわちカーボンニュートラルの状態を目指すものです。
企業は海洋酸性化に対処するためにどのような取り組みをしていますか?
-企業では、商船三井が二酸化炭素排出量の少ないフェリーの開発や、セブン&アイホールディングスが水質改善に寄与する海底の植物の栽培など、環境に優しい取り組みを行っています。
SDGsとは何であり、海洋酸性化に関連する目標は何ですか?
-SDGsは持続可能な開発のための17の世界共通目標であり、海洋酸性化に関連するのは「14. 海の豊かさを守ろう」という目標で、海洋と海洋資源を保全し、持続可能な形で利用することが求められています。
Outlines
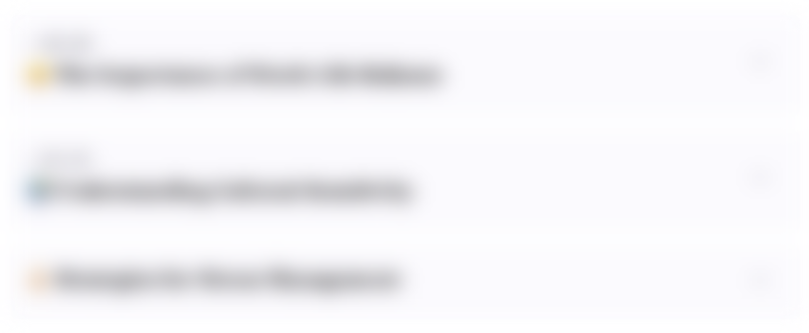
This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.
Upgrade NowMindmap

This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.
Upgrade NowKeywords

This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.
Upgrade NowHighlights
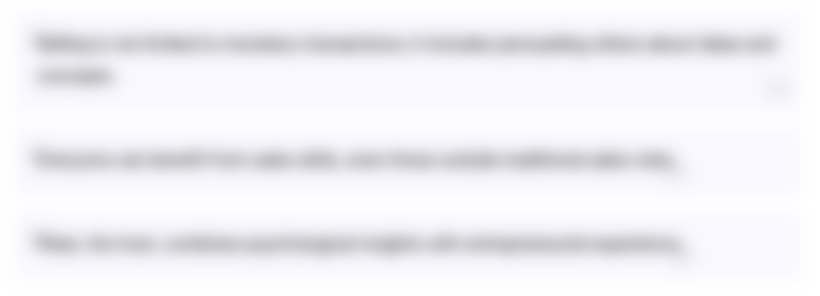
This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.
Upgrade NowTranscripts
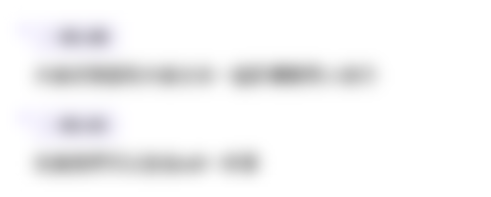
This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.
Upgrade NowBrowse More Related Video
5.0 / 5 (0 votes)






